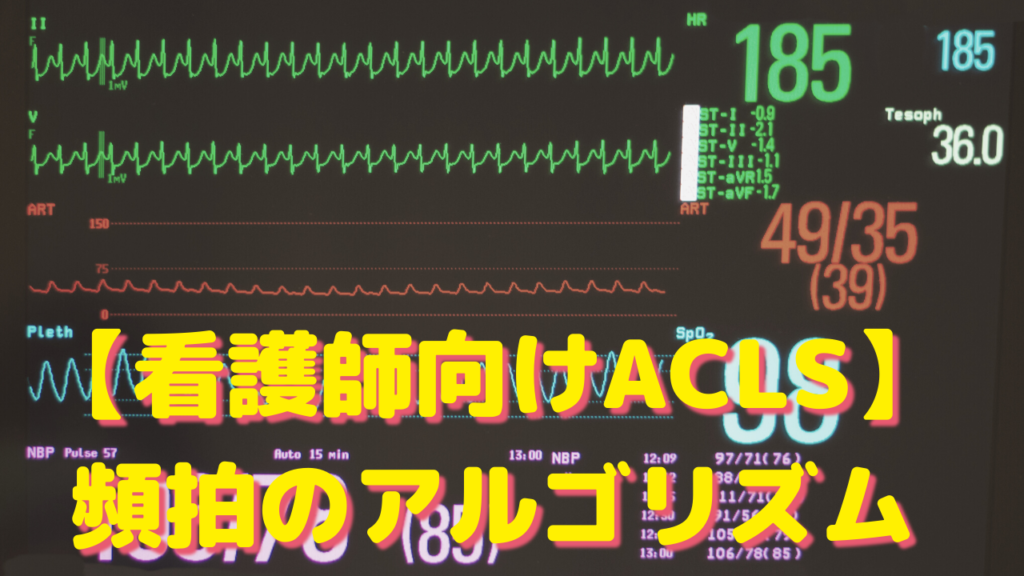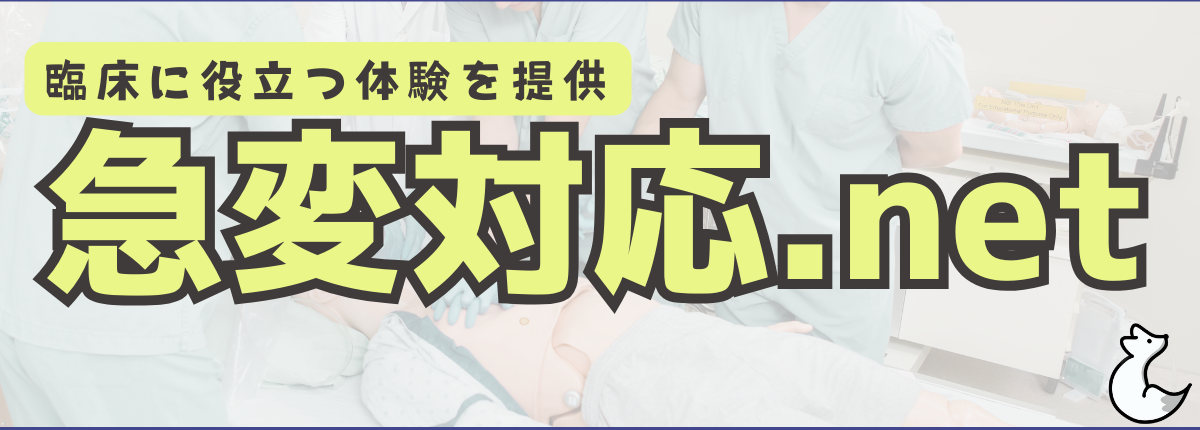うわーHR30bpm!!
心電図苦手だー。わからない。
大丈夫!徐脈のアルゴリズムは非常にシンプルです。
看護師として"波形を読めなくても"初期対応はできます。
ただし、アルゴリズムと一緒に覚えるのが一石二鳥なので早速やっていきましょう。
徐脈の定義
まず、徐脈は通常"心拍数が50回/分未満"と定義します。
更に重要な概念として症候性徐脈という名前があります。その臨床的な基準としては以下の3つです。
1.心拍が遅い
2.患者に症状がある
3.症状は徐脈によるものである
要は、徐脈の特定をしたら、患者の循環が"良好"か"不良"なのか見極めていきます。
そこで、循環が良好な場合はモニタリングと観察になりますし、不良の場合は治療を含めた初期対応に進みます。
状態評価のポイントは、心拍数と血圧だけを循環の判断材料にしているわけでないことを認識しましょう。
心筋梗塞など虚血や心不全に伴う徐脈の場合、胸部不快感や呼吸苦などが存在する可能性があります。更には、心拍が遅いので脳の虚血から意識障害が出現する場合もあります。
このように徐脈が患者の症状を引き起こしているかどうか、または低酸素血症など致死的な疾患によって徐脈が引き起こされてないかもアセスメントしていきます。
症候性徐脈に対する初期対応
症候性徐脈と判断した場合の、第一選択薬はアトロピンです。

アトロピンは過度の迷走神経を遮断する効果や洞結節の興奮頻度が増加するので、迷走神経由来の徐脈に対しては効果があるかもしれません。しかし、完全房室ブロックのような病態の場合は、いくら洞結節の興奮が増えてもHRは改善しない=循環動態が改善しないこととなります。このように器質的な問題の結果生じている徐脈に関しては無効となりますので、次の手を考えなければなりません。
アトロピンを使う場合の用量は、ACLS2020では0.5mg→1mgに引き上げられています。これは低用量で使うと目的と反して徐脈を引き起こすことがあるため、増量されています。
臨床の場合は医師の指示に従ってください。
アトロピンが無効の場合に登場するのが、経皮ペーシングやアドレナリン・ドパミンなどの薬剤となります。

つまり、ここまでの流れは循環器医に必要な専門治療というより症候性徐脈という破綻している循環動態に対する初期対応というイメージをするといいかもしれません。循環動態が破綻しかけている徐脈に対しては一刻も早く専門医の診察と頸静脈ペーシングに繋げるのが大事です。
徐脈管理の基礎
徐脈に対する初期対応としては、
プロバイダーマニュアルに書かれている内容に集約されていますので紹介します。
□徐脈によって引き起こされる自他覚症状と徐脈とは無関係なものを鑑別すること
□房室ブロックの存在及び型を正しく診断すること
□第一選択の薬物療法としてアトロピンを用いること
□経皮ペーシング(TCP)をいつ開始するか決定する
□心拍数及び血圧を維持するために、いつアドレナリンまたはドパミンを開始するか決定する
□複雑なリズム解析、薬物、または管理に係る決定について、いつ専門医への相談を行うべきかを認識する
さらにTCPを思考するための技術及び注意事項を知っておく必要がある
臨床的には、症候性徐脈を認識できれば細かい心電図リズムの判断ができなくても問題ないかもしれませんが、洞性徐脈と房室ブロックの特徴は覚えておきましょう。
さいごに
頻拍のアルゴリズムにも書きましたが、突然心電図モニターのアラームがなった場合や初期対応するときに、PEA(無脈性電気活動)の存在は抑えておきましょう。
この脈拍のある徐脈なのかPEAなのかは初期評価の結果判断できます。
患者の外観に異常がなかったり、反応がある場合はピットフォールにハマりませんが、外観に異常があり反応がない場合、脈拍を触知しない限り判断できません。
もちろんここには"呼吸"などもはいってくるわけですが、我々は血圧やSpO2を無意識に頼りすぎているため、体系的なアプローチを修得しているとはいえないのかもしれません。
BLSの研修でやっている反応の確認はどのような場合に使うのか?
体系的なアプローチでは何を評価しているのか?
この辺りを整理すると見えてくると思います。
ではまた!!
You Tube動画
頻拍のアルゴリズムについてはこちら